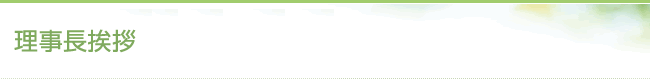TOP > 理事長挨拶

伝統の継承とNext Stageに向けて
COVID-19の第6波の中で、先生方におかれましては、引き続いての患者様の診療、感染対策へのご尽力に対し、心より敬意を表します。
既にホームページでお知らせしました様に、2021年12月1日に日本川崎病学会は、任意団体から法人格を有する一般社団法人に移行しました。私は、2021年4月1日に任意団体の会長を拝命し、引き続き法人化後に理事長に就任致しました。伝統ある本学会が新しい時代を迎え、身の引き締まる思いでございます。社会環境の激変の中で、数年先が読み難いと言われています。学会として、将来像をイメージして、課題を抽出し、今から取り組む必要があると考えます。その為には、学会の伝統と立ち位置の整理が重要で、同時に取り巻く環境を踏まえた柔軟な対応が必須と考える次第です。
故川崎富作先生(2020年6月ご逝去)が、川崎病を報告された1967年から55年が経過しました。前身の日本川崎病研究会の第1回が1981年、世界の川崎病研究者が会する国際川崎病シンポジウムの第1回が1983年に開催されました。2009年に日本川崎病研究会から学会に移行し、2021年には、年1回開催される本会は第41回、2-3年毎に開催される国際川崎病シンポジウムは第13回(日本が担当)が開催されました。川崎病先生とその世代の先生から直に薫陶を受けられた先生、その影響を受けながらこの領域に参入された先生も多いと思います。
本学会は、一疾患を対象とした多領域を跨ぐ集学的な学会です。また日本で発見され、その症例数、高い認知度に基づく急性期診療、成人期に及ぶ長期フォローの経験とそれらに基づく研究実績から国際的に独自性のある学会と考えます。本症の原因は未だ不明であり、様々な角度から研究が進んでいます。2021年11月の第13回国際川崎病シンポジウムは、病因と病態に関わる感染免疫学・遺伝学・血管生物学・病理学・疫学、診断と治療に関わる臨床、社会経済的・Biopsychosocialな課題、冠後遺症のライフステージに応じた医療(生涯医療)について、完全オンライン開催の形で25か国から316名の研究者が集い、熱い議論がなされました。特に川崎病類縁疾患COVID-19関連多系統炎症性症候群(MIS-C)など新たな話題が提供され、次の世代の研究者の参入、家族会の国際的な繋がりが確認され、アジアの川崎病研究者のサテライトの研究会も開催され、新しい方向性が提示されました。学会に参加し、多領域ないし国際的な研究者との交流を通じて川崎病研究に触れ、これから国際的な場で発表するmotivationを得た若手研究者も多いと思います。
2022年は、本学会にとって4つの点で変革の年と考えています。1つ目は、一般社団法人化による学会組織の成熟と社会的役割への期待、2つ目は、急速な国内外の学会活動、研究者交流のデジタル化(Digital transformation, DX)、3つ目は、MIS-Cによる川崎病の病因解明へのinsightの提供、4つ目は、脳卒中循環器病対策基本法・成育基本法による基本計画の開始と学会・学会連合の強化です。
そこで、学会の伝統を踏まえながら、法人の体制整備と共に、以下の活動が重要と考えます。
1 学会支援研究(多領域共同研究も含む)の推進
2 国内の学会間連携、地方の川崎病関連研究会との連携の推進
3 川崎病研究団体の国際的連携、アジア内の連携推進
4 若手育成、生涯学習の機会の提供(学会主催オンラインセミナー開催等)
5ホームページ、交流サイト(SNS等)など広報交流と家族会連携など社会貢献の推進。
これらの活動に向けて、会員をはじめ多くの臨床医、研究者の皆様におかれましては、ご意見とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
(英語版はこちらをご参照ください)
2022年3月
一般社団法人日本川崎病学会 理事長 三谷義英